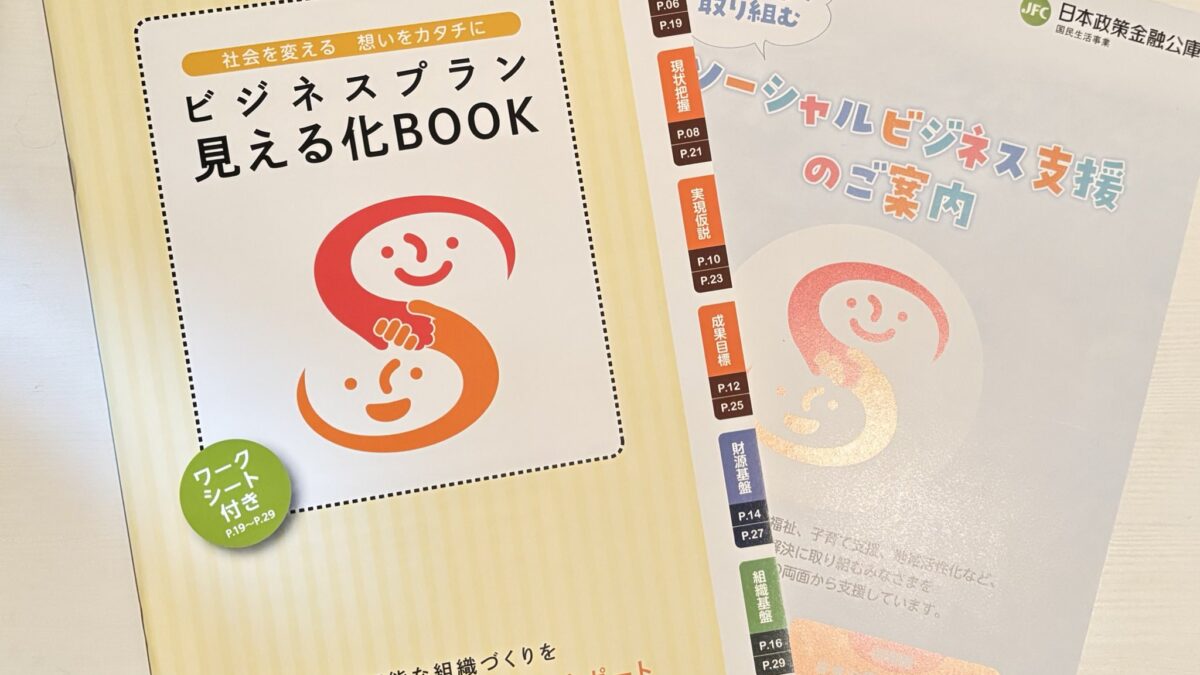はじめに
先日、世田谷区経済産業部経済課主催のソーシャルビジネス勉強会に参加してきました。
地域に根差した活動をしたいと考えながらも、なかなか具体的な一歩が踏み出せずにいました。
今回の勉強会への参加は、その想いを「自分事」として捉え直す良い機会になりました。
普段、Web制作の現場でクライアントの「本当の課題」を見つけることの重要性を感じていますが、今回学んだ社会課題解決のプロセスには、Web制作における課題発見と多くの共通点がありました。
この記事では、勉強会で得た気づきをWeb制作者の視点から整理してお伝えします。
勉強会で問われた3つの本質的な問い
ソーシャルビジネスを立ち上げる際、「良いアイデアが浮かんだ!」と意気込んでスタートします。
しかし、勉強会では事業を始める前に、冷静に自問すべき3つの本質的な問いが示されました。
着想した事業は本当に社会的課題解決になるのか?
自分が「良い」と思っていることが、実は独りよがりになっていないか。
本当に社会的課題解決になるのか?
勉強会では、この問いに向き合うことの重要性が強調されました。
例えば、「高齢者の孤独を解決したい」と地域のコミュニティカフェを始めたとします。しかし、平日昼間に開催しても、高齢者の多くは通院や介護で忙しく、参加できる人が限られているかもしれません。
また、参加費を取る形にした場合、年金生活で余裕のない方は参加を諦めてしまうかもしれません。本当に孤独を感じている人ほど、外出のハードルが高い可能性もあります。
このように、「良い取り組み」と思って始めても、対象者の実際の生活状況やニーズとズレていれば、本当の課題解決にはつながらないのです。
Web制作でも同じことが言えます。
クライアントが「こんなサイトが欲しい」と依頼してきても、それが本当にユーザーの課題解決になるのか、ビジネスゴールに直結するのかを一緒に考えることが、制作者の重要な役割だと感じています。
どうやって事業を継続していくのか?
社会課題解決への熱意だけでは、事業は続きません。勉強会では「継続性」の重要性が繰り返し語られました。
ボランティアと事業の違いは、持続可能なビジネスモデルを持っているかどうかです。
収益構造、運営体制、資金繰り—これらを現実的に設計しなければ、どんなに素晴らしい理念も絵に描いた餅になってしまいます。
Web制作でも、サイトを「作って終わり」ではなく、運用・更新・改善を含めた長期的な視点での提案が求められます。
一時的な盛り上がりではなく、継続的に成果を生み出す仕組みづくりが大切です。
誰のどんな困りごとを解決するのか?
この問いが、最も重要だと感じました。
「高齢者のため」「地域のため」といった漠然としたターゲット設定ではなく、「具体的に誰の、どんな困りごとを解決するのか」を明確にすることが、事業成功の鍵になります。
ターゲットを絞り込むことで、本当に必要とされるサービスの形が見えてきます。
そして、その困りごとを当事者の言葉で言語化できているかどうかが、共感や協力を得られるかの分かれ目になります。
Web制作におけるペルソナ設定やカスタマージャーニーの考え方と、まさに同じアプローチです。
「誰のために、何を解決するのか」が明確でなければ、効果的なWebサイトは作れません。
Web制作における「課題発見」との共通点
これら3つの問いは、Web制作のプロセスそのものだと気づきました。
私たちWeb制作者が最初に行うべきは、クライアントの要望をそのまま形にすることではありません。
- 本当の課題は何か?
- どうすれば持続的に成果が出るか?
- 誰のどんな問題を解決するのか?
—これらを丁寧に掘り下げることが、価値あるWebサイトを生み出す第一歩です。
ソーシャルビジネスもWeb制作も、根底にあるのは「誰かの困りごとに真摯に向き合い、解決策を提示すること」。
その本質は変わらないのだと、改めて実感した勉強会でした。